
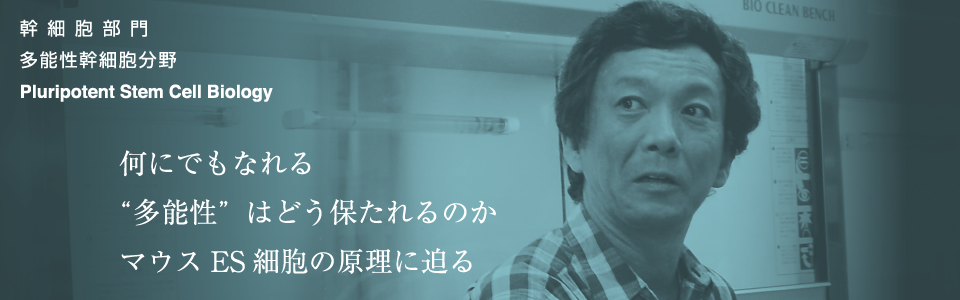
多能性を維持したままどうやって自己複製するのか
何にでもなることができる多能性幹細胞。代表的なものとして、受精卵からつくられる胚性幹細胞(ES細胞)がよく知られています。しかし、その“何にでもなれる”という機能がどのように決まっているのか、そこにはまだ解明されていないことが多く存在します。その謎に挑むのが、マウスのES細胞の多能性維持の分子機構解明を研究テーマとする丹羽仁史教授。「ES細胞は、特定の培養条件のもとでだけ多能性を維持したまま自己複製を繰り返し、培養条件を変えれば分化します。その特定の培養条件でだけ多能性を維持する仕組みとは何か、それが“問い”です」。 多能性幹細胞というと、今はiPS細胞に注目が集まります。「ES細胞で動いている転写因子を体細胞に入れると、ES細胞のような多能性を持つ細胞になるという事実を示したのがiPS細胞ですが、なぜそうなるのかという仕組みはまだ説明できていません」と丹羽教授。研究が進めば、体細胞が一定の転写因子によってなぜリプログラミングされるのか、その“問い”の答えも見つかると、丹羽教授は語ります。
「知りたい」が動機の研究があっていい
丹羽教授は、大学院時代を熊本大学の山村研一教授のもと、ノックアウトマウスをつくる発生工学の最先端で過ごしました。「病気のモデルマウスをつくることが目標で、その中でES細胞をどうやって安定培養するか、その検討が主な研究となり、そこからES細胞に興味を持ちました」。その後、多能性幹細胞を解析するイギリスの大学へ留学し、以来約20年にわたり、この分野の研究を続けています。 ES細胞を扱う研究というと、再生させ何かをつくる、というイメージがわきがちですが、「私の研究は多能性幹細胞そのものの性質を扱うもの。そこから何かをつくる、という研究ではありません」と丹羽教授。マウスのES細胞を研究しているのも、多能性の検証が可能だからです。一時はヒトのES細胞も扱っていましたが、「多能性を検証する一番の方法は、その幹細胞が全身のすべてになれること。マウスはキメラをつくることで検証できますが、ヒトでは不可能です。マウスでやるからこそ意味がある研究と言えます」と丹羽教授は言います。 そんな丹羽教授は、近年の研究は、「何かをつくる」という医学工学的志向が強いと言います。もちろんそういった研究も必要ですが、「一方で、“知る”というモチベーションもあってしかるべき。iPS細胞もいきなりできたわけではなく、一つひとつの分子機能を解析し、知るというアプローチをする助走期間があるから次に進めたわけです。知ることなくつくろうとすると失敗します。“知ること”をきっちりとやらないといけない」。丹羽教授の、基礎研究に対する揺るぎない思いです。
世界中で自分だけが知っている瞬間がある
そんな「研究」の魅力を、丹羽教授はこう語ります。「知るタイプの研究、つくるタイプの研究、そのどちらも、ある瞬間、世界中のだれも知らないことを自分だけが知っている、その状態をつくることができることです」。本で何かを学ぶことはできても、それはすでに誰かが知っていること。「インターネットも同じです。検索して知ることは、すでに誰かが知っていることですよね。そうではなくて、ある瞬間純粋に、世界中で自分だけが知っている状態になることができるのが研究の現場です。自己満足かもしれませんが、それがモチベーションになってもいいはずです」。 もちろん、そんな瞬間を味わうためには努力が不可欠。「努力すればそういう瞬間を持つことができる。研究の世界はプロ野球と同じで、ドラフトである程度選抜されて入っても、一軍で活躍できる人はわずか。そういう世界なんだという覚悟と強い意志をもって来てもらうべき世界だと考えています」。